邦楽
2025年11月10日 (月)
世代もジャンルも超えて「共振・共鳴」する音楽会
INTERVIEW
篠崎史紀(ヴァイオリン)・今藤長龍郎(長唄三味線方)
2026年2月に「響きあう和と洋」シリーズの九州公演を開催します。2017年に「紀尾井午後の音楽会 花鳥風月 其の弐―花―」で共演された、ヴァイオリンの篠崎史紀さんと、長唄三味線方の今藤長龍郎さんが再び共演する本公演について、お二人にお話を伺いました。
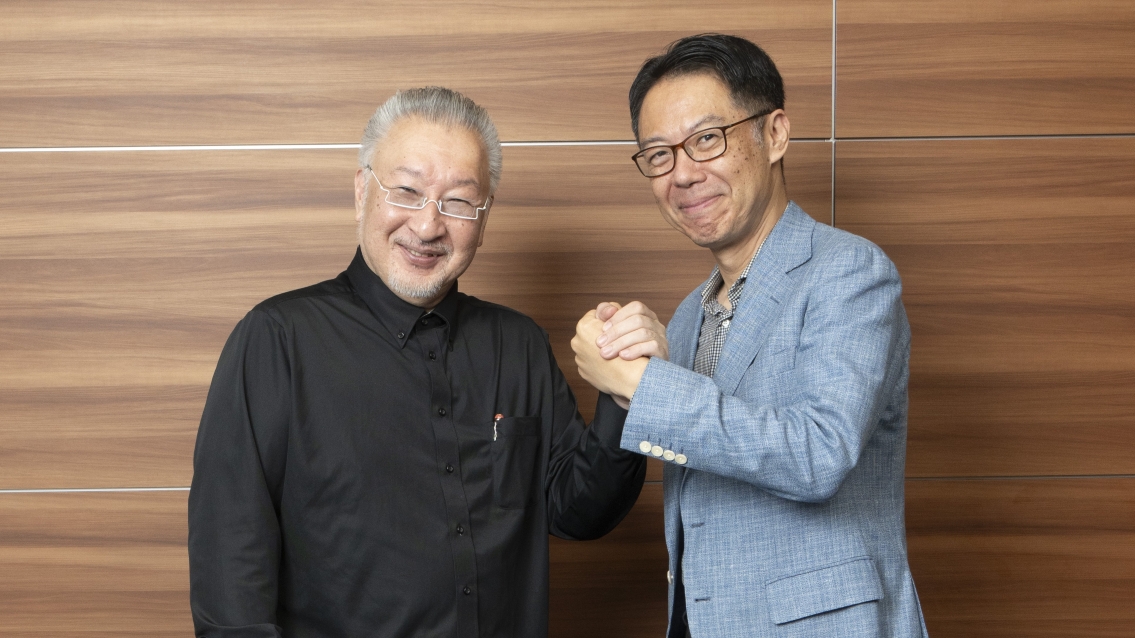
2017年の初共演時の印象はいかがでしたか?
篠崎 ヴァイオリンと三味線は、普段演奏する音楽ジャンルは違っても「音楽」という根っこは一緒で、そこは何の違いもないのですが、音が減衰していく楽器(三味線)と持続する楽器(ヴァイオリン)が一緒に奏でる、というところが非常に興味深かったし、そこが一番面白かったですね。
今藤 そうですね、私は音が減衰していく楽器を使いますが、いかに音を伸ばすか、を意識しているんです。三味線は弦を撥で弾いた瞬間から音は消えていくけれども、その音をどれだけ伸ばせるか。私の師匠の今藤綾子先生は、そういう音をさらっと出せたのです。本当に尊敬していますし、自分はまだまだ修行が必要だなと感じます。
篠崎 減衰していく楽器ってかっこいいですよね。
今藤 逆に、まろさん(篠崎さん)の演奏を聴いていて感じたのですが、持続する音を「線」とすると、その「線」の中にちゃんと「点」があるんですよ。持続しながら「点」を作っていくのは難しいんじゃないかと思うのですが。
篠崎 そうですね、簡単に言えば自分の音を聴くこと。音をよく聴いていれば、理想に近づくことができると思っています。
そもそも、お二人が楽器を始めたきっかけは?
今藤 伝統芸能というと、代々の家系で・・・と思われがちですが、母は藤舎流笛方家元の家系ですが、父はサラリーマンでした。父は、サラリーマン時代に趣味で始めた長唄で「今藤尚之」の名を許されて、プロに転身したんです。それもあってか、父からは一度も「やれ」とも「やるな」とも言われたことはありません。幼少期は音楽教室でピアノを習っていたくらいですから。母も家元家系ではあったものの、本人はまったく演奏しなかったそうなんです。とはいえ、父が出演する歌舞伎の舞台はよく観に行っていて、小学校5年生の時に「自分も三味線を弾いてみたい」と思ったのが始まりです。そこからは夢中で楽しくて楽しくて。お稽古がきついこともあったけれど、ずっと好きで、今に至る。というところでしょうか。
篠崎 私は、いつどうやって始めたのか、やりたいかやりたくないかを考えたかどうかも覚えていないんです。両親が音楽教室をやっていましたから、生まれた時から家に楽器を習いに来る子どもたちが毎日出入りしていたし、音楽は生活の一部であって、当たり前にあるもの。私にとってヴァイオリンを弾くことは、歯を磨くのと同じくらい、生活に欠かせないものなんです。私も両親からやれとか、やるなとか一切言われたことはないですね。ただ一つ、ずっと言われていたのは「楽器が弾けると世界中の人とお友達になれるよ」本当にそのとおりですよね。4歳の時にヴァイオリンを背負って動物園に行き、いきなり象の前で弾き始めたらしいんですよ。何故って?「象とお友達になりたいから」と答えたそうです(笑)
ヨーロッパ留学中に分かったことは、言葉が通じなくても音楽で交流できる。人種や宗教の壁があっても、音楽でなら通じ合えるんです。
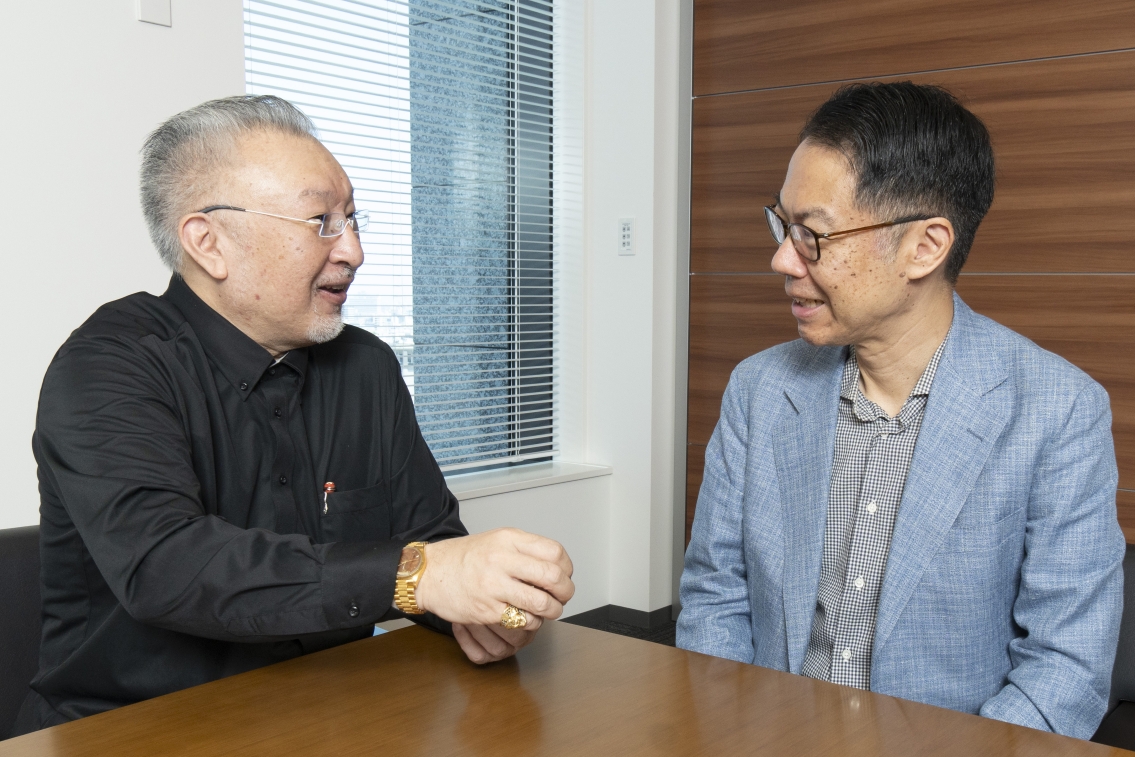
再共演となる熊本民謡「ヨヘホ節」「五木の子守唄」によるラプソディーについてお聞かせください。
篠崎 「ヨヘホ節」や「五木の子守唄」を聴いたことがない方も、どこか懐かしさを感じるはずです。日本人のDNAに刻まれたものなんでしょうね。聴くと、心地よいなと思える曲です。
今藤 前回はまろさんと二人で演奏したのですが、熊本市民会館での公演は、箏、十七絃、合唱が入った大きな編成にバージョンアップしますから、また違った印象になると思うので楽しみにしてください。響ホール(北九州市)公演は二人での演奏になりますが、譜面を拝見しましたら、前回よりもブラッシュアップされていて、さらに進化した作品をお届けできると思います。
最後に、演奏会に向けて一言お願いします。
篠崎 この公演は「共振共鳴」が大きなテーマになっていると思います。響ホール公演には「共鳴する音楽会」という素晴らしいタイトルがついていますが、まさに楽器と楽器が共鳴し、楽器と人が、人と人の心が共鳴する、そんな演奏会になればと思います。出演者もベテランから中学生(ピアノの鈴木れあ)までいますから、現在から未来へつなぐ、というテーマも隠れています。
今藤 それに、西洋音楽と邦楽と一緒に演奏する音楽会って、あまりないですよね。それは人が勝手にジャンルで分けてしまっているからですが、ジャンルを超えて一つの音楽として「共振共鳴」する現象がホール全体に起きる。その体験を、ぜひ幅広い世代の方に味わっていただきたいですね。
取材・構成/紀尾井だより編集部
撮影/武藤章
響きあう和と洋 全国公演
2026年2月7日(土)14時開演
くまもと大邦楽祭実行委員会×日本製鉄紀尾井ホール
邦楽新鋭展 meets 紀尾井午後の音楽会
2026年2月8日(日)14時開演
北九州市立響ホール×日本製鉄紀尾井ホール
共鳴する音楽会~東西の伝統が音楽で響き合う~

篠崎史紀(しのざきふみのり/ヴァイオリン)
愛称“まろ”。1963年北九州市出身。1981年ウィーン市立音楽院に入学。翌年ウィーンにてヨーロッパデビューを飾り、その後ヨーロッパを中心に活動をする。1988年に帰国後、群響、読響を経て、1997年NHK交響楽団のコンサートマスターに就任。以来“N響の顔”として国内外で活躍し、2025年3月惜しまれながらもその任を退く。ソリスト、室内楽奏者、指導者として、国内外で活躍中。1996年より東京ジュニアオーケストラソサエティを設立。2004年より銀座王子ホールにて「MAROワールド」を開催している。1979年史上最年少で北九州市民文化賞、2001年福岡県文化賞、2014年有馬賞受賞。 北九州文化大使。WHO国際医学アカデミー・ライフハーモニーサイエンス評議会議員。使用楽器は1727年製ストラディバリウス(株式会社ミュージック・プラザより貸与)。
特選プロフィール
1963年1月18日吉日。
篠崎家に待望の男児が誕生。
その名はふみのりくん。
3歳でウルトラセブンと出会い、将来の夢は宇宙人になること。
空を飛ぶための練習はかかさず、布団の上で習得するものの、小学生に上がる前に宇宙人になれないことを悟る。
だが、サンタクロースの存在を信じる純粋な少年でもあった。
再び、衝撃的なヒーローに出会う。
その名は仮面ライダー。そこは単純なふみのりくん、宇宙人になれなくても改造人間ならとシフトチェンジ。
まずは仮面ライダーの本職であるバイク乗りになろうと、当時、爆発的人気を博した「仮面ライダー自転車」に目を付ける。
サンタクロースにお願いの手紙を大量に書き、切手を貼らずにポストに投函し、自転車の到着を今か今かと待つ日々を送る。
良い子にしていたらサンタのおじさんが来てくれることを信じていたふみのり少年、精神面鍛錬を欠かさず行い、善と悪についての基本形をマスターする。
その甲斐もあり、念願の仮面ライダー自転車(補助輪付き)を手に入れ、猛練習を始めると同時に、サンタクロースが持ってきたもう一つの大きな袋。
中には巨大なヴァイオリンとサンタクロースからの手紙が入っていた。「これはヴァイオリンの親分です」とサンタクロースからのメッセージに、負けず嫌いなふみのり少年、その親分を自分の子分にしてやろうとチェロを必死に弾き始める。
その後ピカピカの一年生になり、学校では「防空壕跡事件」「カマキリ孵化事件」「カエル逃亡事件」「壁チョロ逃亡事件」、その他多数の事件の首謀者として注目を浴び、帰りの会で学級委員長の女子から毎度話題に上がる。
スクスク育った少年は、宇宙戦艦ヤマトと銀河鉄道999に出会い、雪とメーテルに心を奪われそうになるが、ゴジラの魅力には勝てず踏みとどまる。
その後、ジェームスボンドとの衝撃的な出会いによって段ボールで黄金の銃の製作に勤しむ。
改良に改良を重ね、ついにゴム飛ばし銃の製作に成功。MI6を目指し、007の次の番号である008のライセンスを取るため鉄棒で飛行機飛びをマスターし、またもや注目を浴びる。
懲りない少年である。
15 歳でふみのり青年の今後を決める出会いが訪れる。それは、スターウォーズ との運命の出会いである。
それまでになかった善悪の主人公の逆転、映像でピアノ線の見えない飛行機に感銘を受け、将来はダースベイダー を目指そうと心に決める。
しかし同時期にヨーロッパに渡り、007で見た風景を実際見たことによって再度007熱が出てしまうところが流されやすいところである。
その後、語学習得のため、当時最先端だったVHSのビデオデッキを購入し、スターウォーズ のビデオを暗譜するまで繰り返し観るという前人未到の荒業をやってのけ、語学ではなくフォースを習得。現在に至る。

今藤長龍郎(いまふじちょうたつろう/長唄三味線方)
1969年東京都生まれ。1979年今藤綾子(人間国宝)に入門。1985年今藤長龍郎の名を許される。1991年東京藝術大学音楽学部邦楽科を卒業。2004年アテネオリンピックシンクロナイズドスイミング「ジャパニーズドール」三味線パート演奏。2005年ビクター伝統文化振興財団賞奨励賞受賞。2025年松本幸四郎主演初春大歌舞伎「陰陽師 鉄輪」作曲。長唄五韻会同人、現邦連会員、創邦21同人。国立音楽大学非常勤講師。
特選プロフィール
1969(昭和44)年4月に誕生予定だったが、3月に季節外れの大雪となり母が雪道で滑り転倒、思いがけず産まれる。
調子笛(ピッチパイプ)をおもちゃ代わりに育つ(録音テープがどこかに残っている)。
両親は公立幼稚園入園を希望し、手続きに行ったがすでに満員、近隣のお寺が経営する幼稚園を紹介され、そちらに入園となる。
幼稚園に大手音楽教室が併設されており、ピアノの音色に魅力を感じたらしく、4歳からピアノ(幼児科)を始める。どうやって五線譜を覚えたかは記憶に無い。
自宅は小さなアパートだったためピアノが置けず、知り合いからいただいた電子ピアノで練習する。最初の先生は優しかったが2年目の先生は厳しく、弾けないと手を叩かれた記憶があったが、それがうまくなろうと思うルーツだと思っている。
そのままピアノは続け、小学生時代は目黒にある大きなセンターに通う。先生の勧めでピアノ作品の作曲も始めるが、作品ができない苦しさ、入賞するためのコード進行や作品パターンが辛くなり、小5で作曲は一旦やめる。
(この頃、三味線を始めている)
中学時代は、指導いただいた先生からブルグミュラーかベートーヴェンのソナタを2台のピアノに編曲する課題があり、週によっては22時過ぎまでセンターに残り先生や同級生と編曲や印刷を頑張る。同時期にあったピアノの発表会でベートーヴェンのソナタをまずまず弾けたが、演奏の後、客席に行って聴いていると衝撃的な演奏に出会い、自分の力の未熟さを痛感する(その演奏は、横山幸雄さんです)。
入学した高校で音楽授業が盛んだったため(一年中混声合唱)、毎回ピアノ伴奏。そして、ピアノ伴奏として勧誘を受けたが本当は男子部員不足という合唱部に騙されて入部。結果的に3年間居て、最後は部長になって、やっと伴奏を務める。
学校の音楽祭での学年合唱では、1年生はベートーヴェンのハ長調ミサ、2年生は2台ピアノでアイーダを伴奏。3年生は合唱部の「島よ(大中恩作曲)」を伴奏した。
その当時、校内で人気のバンドがあり、そのギタリストの方がのちに再会する沢井比河流さんで、同じ音楽ゼミ(学校では自由研究と言っていました)となり、和楽器談話及び比河流さんの演奏も聴かせていただいた。素晴らしい演奏だったのを覚えている。
そのゼミでのラストステージは、ショパンのスケルツォ第2番であった。
中学時代一緒に学んだピアノ仲間は、
チェンバロ奏者
ピアノ指導者(ミュージカルの練習ピアノなども務める)
ピアニスト
NHK職員
など、多岐に渡る。
高校時代の仲間は、
フルート奏者
税理士
サラリーマン
など、またまた多岐に渡る。
